2016年12月の読書
平田雅博著『英語の帝国ーある島国の言語の1500年史』(講談社メチエ、2016.09)
題名に魅かれて読んだ。
とても史実が細かくて前半はちょっと退屈だったが、現代日本の英語教育の章になるとがぜん面白くなる。前半はその伏線で、やはり歴史的な厳密な論証がないと無責任な主張に終わってしまうということを実感させられた。
英語は今や国際共通語である。デファクトスタンダードというやつだ。
私が以前勤めていた大学はいち早く英語重視の方針を打ち出し、多くの外人を雇い英語で授業をし、卒論も全員英語で執筆を義務づけた。
英語はどのようにして今日の地位を築いてきたのだろう。
第一段階はイングランドからウェールズ、スコットランド、アイルランドへの普及というか、征服だ。
第二段階は英語を話す人々のアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどへの植民。現地語と現地人は抹殺され、英語が母語として定着している。
第三段階は植民地。インドやアジア、アフリカの国々を植民地にして英語を強制する。現地の言葉ももちろん存在するが、英語が公用語、共通語となってしまった。
土地の征服は「悪行」だと分かるが、英語は国を文明化し統一した「善行」と思われやすい。
第四段階は、中国、韓国、エジプト、ロシアなど、外国語として英語を、それも強制されてないのに自ら進んで英語教育を行なっている国々で、日本も当然ここに入る。いわば 「自発的植民地」だ。
この本の表紙に、ロビンソン・クルーソーの絵が載っている。島で唯一の人間であるフライディに英語を教えているのだ。
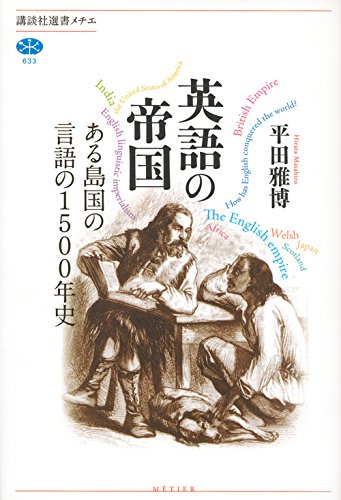 ロビンソンには彼の母語を学んで友だちになろうという気は最初からない。まず自分を「マスター」と呼ばせ、英語を教えて忠実な召使いとして仕えさせようとしたのだ。そうか、言われてみればそういう話だった。
ロビンソンには彼の母語を学んで友だちになろうという気は最初からない。まず自分を「マスター」と呼ばせ、英語を教えて忠実な召使いとして仕えさせようとしたのだ。そうか、言われてみればそういう話だった。
森有礼の英語導入論にも触れられている。
森が意図したのは英語そのものの採用ではなく、たくさんある例外事項、不規則変化を取り除いて簡単にした日本人用に特化した英語であり、それはすぐ断念したということだ。その後日本人は西洋の文明を次々に翻訳して取り入れてきたわけである。
現在の英語教育推進者の共通項目である
「英語を英語で教える、教える人はネイティブスピーカーが望ましい、できるだけ幼いうちから英語教育を始める」
などという理論は1966年にウガンダで開催された、アフリカに英語を普及させるための「マケレレ会議」の信条をそのまま引き継いだもので「前論理的」だと著者は言う。そうだったのか。
日本に引き寄せても、東北弁などの方言、アイヌ語や琉球語、そして朝鮮占領時代の日本語強制など論点はたくさんあるだろう。フランスでは英語とどう向き合っているのかも気になった。
そして、コメニウスを始めとした世界共通言語の主張についても検討してみる必要があるなあ。
2016年12月30日 記載
佐和隆光著『経済学のすすめ―人文知と批判精神の復権』(岩波新書、2016.10)
新聞の書評欄で紹介されていたので読んだ。
昨年の文部科学省の人文軽視の方針に反対して書かれた本だと。
経済学は人文知と一番遠い学問と思っていたのでちょっと意外だった。
ぼくは知らなかったのだが、著者は昨年度まで滋賀大学の学長であり、学長の立場から文部科学省を批判する論陣を張ってきた。その「到達点が本書」だという。
著者は「人文知を排斥する国家は全体主義に成り果てる」と断言する。
大学の国際ランクを上げるには、人文社会の学者に英語の論文をたくさん書かせ、教育にもっと公的資金を投入すれば良いのだ。
経済学は有用とされているが、それは政府の政策によっての「有用さ」であると言う。アベノミクスへの批判もするどい。
マルクス経済学がほぼ消滅した今、経済学はアダム・スミスから始まりフリードマンに代表される新古典派とケインズ派だ。
アメリカの民主党はケインズ派、共和党は新古典派である。アベノミクスはどちらでもなく「国家資本主義」なんだそうだ。
著者はアメリカで学び教えた経験豊富な計量経済学者であるが、行きすぎた計量経済学には批判的だ。ピケティは MIT の助教授に抜擢されたのだが2年で見切りをつけたのは「数学への偏執狂ぶり」を批判してのことだそうだ。
それに、数学に偏したアメリカの経済学の学生はそれでも日本よりは古典をたくさん読んでいるという。
スティグリッツやクルーグマンといった、数理的な経済分析が評価されてノーベル賞を受賞した学者も、思想的には確固としており、先の選挙ではサンダースを応援していたそうな。
それに対して日本の「エコノミスト」と称される人々は学会にも所属していないし政府の政策に「有用な」データを出すだけという。
センター試験や政府の審議会の批判とか日本の学生が勉強していないことなど、話があちこち飛びすぎて漫談調のきらいがないでもないが、読んで痛快な本であった。
濱田武士著『魚と日本人』(岩波新書、2016.10)
ぼくは肉より魚が好きだ。
食べ方も上手だと自負している。食べ残しはほとんど出さない。
ただ鮮魚を捌くのはできないが。
同居している妻は肉が大好きで、魚といえば刺身のことだ。ふつうに魚を食べるとすれば冷凍の加工品がほとんど。
元々遠洋漁業の魚は冷凍されて運ばれてくるのだし、最近の冷凍技術は優れているから不満はないのだが、もう少し魚を食べる機会を増やしたいと思っている。
この本は、魚を食べる、魚を扱う、魚を獲る、その三方面から魚の問題を総合的に論じており、改めて考えさせられることが多かった。
まず食べるということだが、前述の通り魚好きのぼくでさえ食べる機会が減っているのだから私の娘などはまず食べてないと思う。
それに、昔風の魚屋さんがもう存在しない。スーパーの一角に場所を占めているだけだ。おお、何でも売っているはずのコンビニではまだ鮮魚を扱ってないな。でもコンビニで鮮魚を扱うようになったら、どんなことになってしまうのだろう。心配だ。
魚市場については、最近豊洲移転が問題になっているけど、全国的に見て魚市場がとても大変なことになっているということは、この本で初めて知った。
それと、漁業の衰退。漁獲量も減っているし、そもそも漁師が減っている。農業や林業の衰退が叫ばれて久しいが、漁業はもっと大変なようだ。さらにグローバル化の流れで、果物や肉と同じく、国内産は手間ひまかけた高級品、大衆が手にできる安価なものは外国産で不安、という棲み分けになってしまうのかも。
かつて高知に住んでいた頃、近所のスーパーで売っていた魚は東京ではめったに見られないような近海物が多くて、安値でとても美味しかった記憶がある。
和食、その中心である魚は、外国人旅行者向けの高級品ばかりという具合にはなってほしくないものだ。そんなことはこの本には書いてないのだが、いろいろ心配してしまった。
そうそう、今のマンションに転居してから、グリルの調子が悪いのか魚が上手に焼けなかった。魚を載せる網を取り換えたらちゃんと焼けるようになった。これからもっと魚を食べるようにしよう。
平原卓著『読まずに死ねない哲学名著50冊』(フォレスト出版、2016.03)
ぼくは昔「哲学概論」という講義を担当していたので、「哲学史」とか「哲学入門」などというタイトルの本はだいたい揃えていた。硬軟取り混ぜてである。
もう講義を担当していないから、この本の存在は知っていたが読もうという気にはならなかった。それに表紙がちょっと怖じ気づくようなものだったし。
先日書店に行ったら、表紙がイラストから写真に換わっていた。だから親しみが増したわけではないのだが、他に三冊ほど買ったのでこれもついでに買ってしまったのだ。せっかく買ったのだから読まなくちゃ。

 表紙の女の子が枕にしているのは、ぼくが学生時代に出版された中央公論社の世界の名著シリーズの一冊。どの巻かまでは見えない。それと岩波のプラトン全集の第9巻ゴルギアス。「現代フランス哲学」という背が見えるがそれ以上は不明。それにヴィトゲンシュタイン全集第1巻。
表紙の女の子が枕にしているのは、ぼくが学生時代に出版された中央公論社の世界の名著シリーズの一冊。どの巻かまでは見えない。それと岩波のプラトン全集の第9巻ゴルギアス。「現代フランス哲学」という背が見えるがそれ以上は不明。それにヴィトゲンシュタイン全集第1巻。
表紙には6万部突破!と刷ってあり奥付には14刷とある。
著者はまったく無名の30歳だ。
50冊が紹介されているがニーチェは3冊という具合で取り上げられている哲学者は34人。特筆すべきなのはニーチェ以降の「現代」が全体の半分のスペースを占めていることだ。
ちなみに、東大教授で権威である熊野純彦の『西洋哲学史』(岩波新書、2006)は全30章のうちヘーゲルより後に充てられているのは4章分にすぎない。
ぼくは現代は苦手だ。だから講義ではいっさい取り上げたことはない。でも少しは読んでみなくちゃ死ねないわけだ。
著者は正直に多くの哲学書は難しいと言う。
「カントやヘーゲル、フッサールなど、そもそも何をいわんとしているのかさえ、ほとんどつかめない」。だから、外国語から日本語に翻訳された哲学書をさらに翻訳する必要がある。
・カントは「よほどの天才でなければ、まず挫折する」
・ヘーゲルは「ヘーゲル語」に慣れないと、ほとんど読み解くことができない。
・フッサールの難しさは哲学の歴史上随一。
・ハイデガーを「わからないからこそすばらしい」と信奉する人も少なくない。
・レヴィナスの著作はどれも読みにくい。
・フーコーが何のためにこうした批判を行なったのか、ほとんど見えてこない…。
それでも著者は、
・ニーチェの『権力への意志』は「本書を踏まえずして、もはや善悪や美醜といった価値について原理的に論じることは不可能」なほど「力をもった著作」だと高く評価し、
・『存在と時間』は哲学の歴史におけるひとつの金字塔だと断言する。
それにもかかわらず、
・ニーチェの思想をそのまま受け入れる必要はないし…決してそうするべきではない。
・ハイデガーの文章に惑わされない、強い自律の心が必要
とも書いている。
著者はポストモダンには批判的だ。
・ポストモダン思想の基本の目的は、原理に対抗し、普遍性を否定する点にある。ポストモダン思想は、真理や普遍性に、差異や多様性を対置されて徹底的に相対化した。しかし…「相対化は何も生み出さない」
そして著者は私たち自身の問題意識から試しなおす姿勢で古典を読もうと呼びかけているのだ。
ぼくは改めて、現代哲学は古代ギリシャや近代哲学が提示した問題をちょっと表現を変えて蒸し返しているに過ぎないという印象を強くした。
それと、「企投」「対他存在」「贈与」など、原語では特に難しい単語ではないのに漢字の専門用語が怖じ気づかせているという感も強くした。
まだ漠然としているのだが……
日本語では「ある」と「である」は別の意味だ。
There is a pen on the table. ペンが「ある」
This is a pen. ペン「である」
ところがヨーロッパ主要国の言葉が両方の意味を兼ねている。
さらに、
esse, be, être, sein それぞれが動詞としても名詞としても使用可能で、動詞は人称変化する。合成語がたくさんできる。
その辺のことが西洋の哲学、特に「存在論」をやたら難しくしているのではないかと前々から推測しているのだが、これ以上はよく分からない。
2016年12月21日 記載
西洋教育史の本をまとめて読んだ
ぼくは30数年前、「西洋教育史」の担当だった。
最初の赴任地が教員養成系の大学で、周囲には教育哲学、教育行政、教育社会学、教育方法、社会教育、日本教育史などの担当者がいた。
実を言うとぼくはそれまで教育史をきちんと学んだことがなかったので、講義のためにずいぶんたくさんの専門書や概説書を読んで勉強した。
転勤後は教育全般を担当することになって、西洋教育史という講義は担当しなくなった。またその頃から「西洋」とか「教育史」とかいう授業は実用的でないから必要ないという風潮も広まってきた。
ところが、来年の春から「外国の教育」「教育の歴史」「西洋教育思想」という講義を担当することになったのである。そろそろ準備しなければいけないなあと思っていた矢先、
藤井千春編著『時代背景から読み解く西洋教育思想』(ミネルヴァ書房、2016.10.30)
という本が出版されたのでさっそく買って読んでみた。
それぞれの時代状況の中での「思想家の不屈の闘い」を学ぶのが大切なのだという。
各章の前に2ページ分の Introduction が付いており、節ごとに Question がついている。これは教科書としての性格か。読みやすい。
まず好感を抱いたのは、古代の数箇所と現代の章を除いて中心部分を藤井千春氏が一人で書いていることだ。このような教科書類は何人かが分担執筆するのが普通になっている。それに対して、ジョン・ロックから20世紀の新教育運動までを藤井氏が一気に書いている。
文体は「です、ます」調、文章はとても短くて単純明快。
・「ルソーは、1712年にスイスのジュネーブで、時計職人の二男として生まれました。しかし、母親はルソーが生まれて数日後に死亡しました。」
・「カントは1724年、プロイセンのケーニヒスベルクで生まれ、生涯、ケーニヒスベルク周辺で生活しました。」
・「1782年、フレーベルは、ドイツ南部チュービンゲンの豊かな森が広がるオーベルヴァイスバッハに生まれました。」〔チュービンゲンはおそらくチューリンゲンの間違い〕
・「ヘルバルトは、1776年、ドイツ北部のオルデンブルクに生まれました。」
ところどころに大胆な評価が登場する。
・「ルソーは、父親になることを拒否し続けたのです。」
・ペスタロッチは「八転び七起き」で「転んだままで死去しました」。
・「影の薄いヘルバルト」
など。
「約100年をかけてフランスの公教育制度は完成されました。」
「そして20世紀初頭に〔イギリスの〕公教育制度は完成しました。」
「民主主義は、イギリスでは「改革」を通じて、フランスでは「革命」によって、ドイツでは「上から」達成されたと言われています。アメリカの場合、…「創出」されました。
藤井氏はデューイの専門家らしくデューイと新教育運動の説明が詳しく、それもなかなか良くまとまっている。
「市民革命は、各国の封建的残滓の払拭、絶対主義体制の打破、資本主義の発展を志向し、社会的身分編成、近代型資本主義、市民社会、近代民主主義思想などを促進させ、産業革命へと連なる転換期であった。」『西洋の教育の歴史』(ミネルヴァ書房、2010年)24ページ。
こういう難しい表現は見当たらないので安心だ。
講義の際の参考書の有力候補だ。
ついでに、
石村華代・軽部勝一郎編著『教育の歴史と思想』(ミネルヴァ書房、2013.04)
も買ってみた。
これは前半が西洋、後半が日本である。
帯には「教員志望者必携、座右の書」「教員採用試験頻出の人物の思想と実践をわかりやすく解説」とある。ここまで言われると逆に学生には勧めにくい。
出だしからして、ソクラテスとプラトンの名前のギリシャ文字が間違っており意欲をそがれる。
最後は日本の大正自由教育で終わる。戦中の教育や戦後改革にはまったく触れられていない。不満が残る終わり方だ。
ミネルヴァ書房からは
2010年に『西洋の教育の歴史』が出版されており、
2013年の『教育の歴史と思想』そして
2014年の『時代背景から読み解く西洋教育思想』と、
どういう棲み分けをしているのだろう。
また最近出版されたものとして
斉藤利彦・佐藤学編著『新版 近現代教育史』(学文社、2016.03)がある。
これも読んでみた。
1章が古代ギリシャとローマ、そしてコメニウスなのだが、全体の流れからしてまったく不必要だ。
2章がおそらく近代、3章が現代ということなのだろう。扱われているのはイギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、ロシア、中国だ。近代はそれでいいのかもしれないが、現代はそれ以外の地域、例えば北欧やラテンアメリカ、アフリカも加えてほしかった。12人の分担執筆なのだが、誰か書ける人がいなかったのだろうか。
また、国連やユネスコの活躍も加えてほしかったな。ぼくもあまり知らないのだが、子どもの権利条約など触れることはたくさんあると思うのだ。
各国の説明の分量はとても少ないので、これだけで「外国の教育」という講義のテキストにするにはちょっと厳しいと感じた。
もう一冊、検討しておくべき新刊本がある。
眞壁宏幹編著『西洋教育思想史』(慶應義塾大学出版会、2016.04)
この本はとても分厚い。680ページもある。文字も小さいからミネルヴァの藤井編の3.6倍の文字量がある(値段は1.5倍)。2、3日では読み切れない。もとい、読みごたえがある。
編者の眞壁によれば、「教育思想」とは広い意味で「次世代形成」という営みに取り組む思想であり、独立した思想となって成立するのは17世紀後半、具体的にはコメニウス以降だ。そして教育思想史の中心は18世紀の啓蒙主義であり、古典的教育学が誕生するのはペスタロッチ以降となる。ヨーロッパ近代に生まれた教育思想は20世紀末に終焉を迎えたように見えるが、新しい「人間形成論」に依拠した「教育思想」の構想の可能性を探る、というのがこの本の基本的な立場のようだ。
分量が多いから説明も当然詳しい。普通の概論書では扱われない人物、例えばフランクリンやエルヴェシウス、シラーなどにもかなりのスペースが割り当てられている。
最後は分析的教育哲学、ブルデュー、フーコー、アリエス、イリイチへの短い言及があり終わる。
本文中に挿入されている写真には出典が付けられており、学術書の体裁を取ろうとする意気込みが伝わってくる。執筆者は14人。
研究者が読むには良いが、授業で学生のテキストに指定するのはちょっと躊躇する。
さて、ぼくとしてはコメニウスの解説がどうなっているかも気になる。
コメニウスはラテン語名であり、チェコ語ではコメンスキーだということが知れ渡って以後も、ファーストネームの方は「ヨハン」というドイツ語名で書かれることが多かった。
眞壁編も藤井編も「ヨハネス・アモス・コメニウス」となっている。良かった。
ちなみに、現行の Wikipedia の「本名は、ヤン・アーモス・コメンスキーという。コメニウスはラテン語の執筆活動名」という説明には首をかしげる。
ちょっと細かい揚げ足取り。
・石村編の参考文献が稲富栄次郎訳『大教授学』となっているのはちょっとびっくり。
・斉藤編が「コメニウスは、チェコスロバキアのモラヴィア出身」となっているのも変だ。「チェコスロバキア」という国はコメニウスの生存中も現在も存在しないのだから。
・眞壁編、本文中は「ヨハネス・アモス・コメニウス」となっているのに注が John Amos Comenius となっているのは残念。それと、『大教授学』は『教授学著作全集』に「収録された後、1657年に出版された」というのは微妙に不正確。全集が出された後に単著として出版されたかのように受けとられてしまう。事実は『大教授学』は1657年に全集に収録されたのだが。
なお、藤井編の読書案内に『パンパイデイア』が挙げられているのは特筆すべきだ(ただし本文中に言及はない)。
2016年11月17日 記載
日本語の本三冊 その他
今月も日本語の本を読んだ。
まず
庵功雄著『やさしい日本語』(岩波新書、2016.08.19)
題名に引かれて買ったのだが、
「やさしい日本語」とは、日本語を母語としない人々、要するに外国人にとってやさしい日本語のことらしい。
著者の問題意識は、これから外国人の移民を必然的に受けれざるを得ない、そして「多文化共生社会」にならざるをえない、その状況の下で、日本語をどう考えるかということだ。たしかに、外国人でも短期間で習得できる日本語教育を確立しないと、移民を大量に受け入れても大変なことになってしまうことは容易に想像がつく。そして「やさしい日本語」は聾唖者にとっても、日本語を母語とする人々にとっても重要なのだ。
そういう本だとは知らずに購入したものの、けっこう面白かった。
まず、公文書が外国人にとっては理解しにくい、いや日本語を普通に話す人にとっても公文書は分かりにくい、わざと分かりにくくしているのではないかと思われるほどだ。そこで、いくつかの自治体では「やさしい日本語」の導入が進んでいるという。横浜市はその先進らしい。知らなかった。
さっそく横浜市のホームページをみたら、たしかに「やさしいにほんご」のコーナーがあった。
例えば、最新の「広報よこはま10月号」の市長挨拶では、
「…」と思われたことはないでしょうか。
という表現が
「…」と思いませんか。
と書き直されている。
また、「一般会計決算の概要」では、
「市税収入は対前年度0.1%の減となり、3年ぶりの減収となりました」という表現は、
「市に入る税金は、2014年度より 0.1%少なくなりました。入ってくる税金がへったのは 3年ぶりです」となっている。
なるほど「やさしい(優しい、易しい)」表現になっている。
外国人が日本語を学ぶのは、日本人が日本語を学ぶやり方と同じではない。日本の小学一年生が学ぶ漢字は80字だが、それは日常生活で使用頻度が高い漢字というわけではないので外国人が小学一年生の教科書を使ってもしかたがないのだ。たしかにその通りだろう。
また意味が分かればいい語と実際に使える語(これを産出レベルと呼ぶ)は区別する必要があるという。著者が挙げている例は、「右に行くと/右に行けば/右に行ったら」という、日本人でも難しい使い分けは、使う場合はまず「たら」一つだけを採用するというのだ。
ぼくらが外国語を学ぶ場合も、読んで意味が分かればいい表現と、実際に自分で使いこなせなければならない表現とを区別して学習できたら良かったと思う。(もちろん、いろんな表現が使いこなせたらいいにこしたことはないだろうが。)
(おっと、使いこなせるといいな、使いこなせればいいな、使いこなせたらいいな、この三つの違いは何なんだろう。連想したのは、ギリシャ語の接続法現在、接続法過去、接続法現在完了、この三種の意味がほとんど同じでニュアンスだけ違うということ。連想しただけで、どう関係するのかは分からないが)
英語が国際語の地位を勝ち得たのは、大英帝国やアメリカの覇権という政治的影響もあるだろうが、フランス語やドイツ語に比べて文法事項が簡単だ(というより、単純な方向に変化してきた)という面も大きい。小学生から英語を学ばせようという風潮が強いが、外国人に簡単に学べるような日本語(ネイティブの美しい日本語ではなく国際語として通じる日本語)を作り上げて行くことも大切だなと思い知らされた。
中村明著『日本の一文 30選』(岩波新書、2016.09.21)
これはまた「やさしい」日本語は「名文」ではないということを主張しているかのような本だ。
まず小林秀雄。
ああ、この人の評論を高校生の時によく読んだなあ、受験に出るから、と言われて。
「(小林秀雄の)この一文を一度もひっかからずに読んで、すんなりと文意をつかむ日本人はめったにいないだろう」と著者の中村は書く。そうか、だから受験に必ず出ると脅かされたんだ。読むたびに解釈が広がり読者の感想が深まっていくならいいけど、そもそも文意がつかめないのならどうしようもないんじゃないか。
川端康成「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」を「こっきょう」と読むか「くにざかい」と読むか、それがいまだ解決していない大問題らしい。川端がノーベル賞を受賞した時の講演「美しい日本の私」は美しいのが日本なのか、それとも私なのか、文法的にはどちらか不明で、それでいいのだそうだ。おそらく美しいのは日本であって、作家の方ではない。でも「美しい秋田の美女」となれば、美しいのはたぶん美女の方だろう。やれやれ。
(日本語だけがあいまいなのではない。ラテン語で amor matris と書いたら「母が愛する」なのか、「母を愛する」なのか、決めかねる。エラスムスの「痴愚神礼讃」は痴愚神が礼賛するのと痴愚神を礼賛するのと両方の意味を兼ねているのだという解説をどこかで読んだ記憶がある。)
含蓄のある文章を書きたいとは思うけど、意味が何通りにも取れるような文は書きたくないなあ。
池澤夏樹『日本語のために』(河出書房新社、2016.08.30)
新聞の書評欄で大きく紹介されていたので買った。池澤編集の『日本文学全集』全30巻の最終巻、いわばおまけみたいなもの。「日本語の多様性を明示したアンソロジー」だそうだ。
けっこう面白い。
日本人がキリスト教の聖書をどう翻訳してきたのか、そして受容してきたのか、その歴史が概観できる。
また、ハムレットのあの有名な台詞がこれまでどう翻訳されてきたのか、6種類の日本語が列挙されている。
「存(ながら)ふるか…存へぬか…それが疑問ぢや」(坪内逍遥)、
「このままでいいのか、いけないのか、それが問題だ」(小田島雄志)、
ふーむ。
特に面白かったのは、終戦の詔書の現代語訳だ。
昭和20年8月15日にラジオで直接これを聞いた人は、雑音に加えて言葉が難しくて、日本が戦争で負けたということ以外、ほとんど理解できなかったらしい。
高橋源一郎訳では末尾の「爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ」は「わたしの思いが、みなさんに伝わりますように」と訳されている。この現代語訳を読むと昭和天皇がとても慈愛に満ちた方に思えてしまう。
学術的な著作としては、
ジャック・ル=ゴフ著、菅沼潤訳『時代区分は本当に必要か?』(藤原書店、2016.08.10)
ルゴフには『中世の知識人』(岩波新書、1977)以来、注目してきた。2014年に90歳で死亡、この『時代区分は本当に必要か』が最後の著書ということらしい。
もちろん時代区分は必要だ。ただ、どのように必要かを常に考慮すべきなのだ。安易に「近代的」と礼賛したり「中世的」と否定したりするようなことには気をつけないと、例えばぼくが取り組んでいる17世紀のコメニウスとは上手に対話できない。
そのコメニウスの著書の翻訳がようやく出た。
 コメニウス著、太田光一訳『覚醒から光へ:学問、宗教、政治の改善』(東信堂、2016.10.15)
コメニウス著、太田光一訳『覚醒から光へ:学問、宗教、政治の改善』(東信堂、2016.10.15)
内容はなかなか難しい。しかし、未だに宗教や政治の対立が続いている世界情勢をみるにつけ、この世界に平和をもたらすにはどうしたらよいかを考え続けたコメニウスの努力には敬意を払いたい。前作の『パンパイデイア』はできるだけ易しい日本語訳にするよう心がけたのだが、この著書についてはけっこう堅苦しい翻訳となってしまった。読者の感想はいかに。そもそも読者がいるのかどうかがまず疑問だ。
詳細については別の所に書いたので、そちらを参照してください。
2016年10月31日 記
きのう読んだ本
テレビの CM の一場面。
車の中のフランス語の会話。
画面の下に字幕が出る。
その「タイヤ」は
「低燃費」なうえに「長持ち」するという。
信じられるか?
それ、◦◦◦◦◦のことですよね。
なぜ、知っている…
最後の台詞がぼくには「チュサヴェ」と聞こえる。
つまり「きみ、知ってるんだ…」あるいは「知っているのか、きみは」だ。
それを「なぜ、知っている…」と訳すとはすごい、と感心。
(ネットで検索したら Tu le savais. でした。ぼくの耳もあてにならない。)
そこで、宣伝で目にとまった本を買って読んだ。
太田直子著『字幕屋の気になる日本語』(新日本出版社、2016.07.05)
映画の字幕というのは、時間の経過では一秒に四文字、字幕の一行は十文字が決まりなんだそうだ。だから当然要約にならざるをえない。
例えば、
I'm not lying. は
「嘘じゃないわ」ではなく「本当よ」と訳す。
You didn't know? は
「知らなかった?」ではなく「初耳?」だ。
ところが、字幕が画面の下に横書きとなると、一行に十四文字入るらしいので、字幕が縦書きか横書きかで訳語が変わってくる。
さらに、吹き替えの場合は、話すスピードによってもっとたくさん文字を詰め込むことができる。
つまり同じ映画の翻訳でも、縦書きの字幕、横書きの字幕、吹き替え、と三種類あるんだという。劇場公開で縦書きだったものを、テレビで放送したり DVD で販売する時は吹き替え用にまた訳し直すんだそうだ。
しかも常に締め切りに追われている。
大変な仕事だ。
だから著者は、最近のもって回ったくどくどしい表現や、やたら丁寧すぎる表現、長ったらしくて結局意味不明な表現は大嫌いらしい。
そういう事例がたくさん詰め込まれているのがこの本だ。いちいちうなずいてしまう。
きのうもテレビを見てたら「入籍させていただきましたので、皆様にご報告させていただきたいと思います」だって。「入籍しましたので、ご報告します」でいいのに。
不祥事を起こした責任者が「心よりお詫び申し上げなければいけないと思っております」は思わなくいいから早くお詫びしろ、と言いたくなる。
だいぶ前に「アリストテレスは死に臨んで毅然としていたように思われる」は、昔の事は誰も目撃したわけではないのだから、いちいち「思われる」「らしい」はいらないと教えてもらった。だからぼくもできるだけ「思われる」は使わないようにしている。
また著者は、やたらと句読点が多い文章にも批判的である。
ぼくの場合、最初に書いた文章はけっこう句点が多く、読み返してほとんどを削除するのが常だ。書くリズムと読むリズムが違うのだ。
もう一つ気づいたこと。
字幕は縦と横で制限字数が違うというのだが、文字数が同じでも縦と横ではなんだか印象が違う。ワープロで書いた文章が、印刷屋から縦書きのゲラで戻ってくると、何だか全然感じが違っていてとてもアラが目立ってしまうのだ。これはなぜだろう。
それにしても翻訳は難しい。
最近読んだ本の一節。
NE.
Ne, ne, ne.
Nikdy.
Nikde.
Ne!
これなんかどう訳したら良いんだろう。
著者の太田直子さんはたくさんエッセーを書いている。ついでに数冊まとめて買ってみた。(おっと、「買ってみた」は余計か、「買った」でいいんだな)
どれも面白かったが、太田さんは今年亡くなったとか。やはり仕事のし過ぎだろうか。
ぼくの知人に大田直子さんというイギリス教育の研究者がいたのだが、若死にした。残念である。
2016年9月24日土曜日
最近読んだ本
辻田真佐憲著『大本営発表 改竄・隠蔽・捏造の太平洋戦争』(幻冬舎新書、2016.07.29)
予想以上におもしろかった。
国家権力の情報操作は、北朝鮮のような特異な国や、70年前の日本だけ、というのではない、今も現実のことなのだ。
一口に「戦前はひどかったねえ」で著者はすまさずに、大本営による捏造を丹念に掘り起こし、その原因を詳しく分析している。
「大本営」は陸軍と海軍が別々で、ちょっとした縄張り意識や対抗心もあったこと、それは今の役所や会社の縦割りと同じだ。
最初、つまり日中戦争の頃の大本営発表はかなり正確で、むしろマスコミの方が大げさで、先走っていた、特に新聞各社間と新聞とラジオの競争が過熱した報道を誘い出していたこと、これも現代に当てはまる。
従軍記者は情報をもらうために軍の意向に反した記事は書かなかったこと、「新聞用紙供給制限令」によって軍に逆らうととたんに紙がなくなること、それは今も教訓だ。
ぼくは「玉砕」という言葉は大本営の専売かと思っていたら、実は「玉砕」が使われていたのはミッドウェー敗戦後一年未満であり、その後は「壮烈なる戦死」「全員壮烈なる総攻撃を敢行」「最後の斬込を敢行」などの発表がされていたことは初めて知った。たしかに、全員戦死でも士気を衰えさせることにはならないのだ。
大本営発表は国民を騙しただけではなく、戦場の作戦まで狂わせたという。
戦果はそもそも正確には分からない。「おそらく撃沈したと思う」と言うパイロットの報告に対し、上官は「確実に撃沈した」と上に報告する。「本当に間違いないか」と確認する雰囲気はなく、さらに大げさに報告が上に挙げられて行く結果、最後は3艦も撃沈したという結論になる。実はその数は国民向けの大げさな数だと分かっているうちはいいが、そのうち撃沈数が現実のものとされて次の作戦が立てられ、沈没したはずの敵艦にやられてしまう、そういうことが続いたそうだ。
こういうことは今でもありそうな気がする。
昭和天皇は「サラトガが沈んだのは四回めだ」と苦言を呈したそうだし、高松宮は日記で大本営発表は「でたらめ」とはっきり書いていたそうだ。
ところでオリンピックの報道で思うのだが、さすがに負けたのを勝ったと報道することはありえないが、負けそうなのを勝つだろうと解説・報道するのも一種の虚構ではないのか。
これまでの実績、ライバルの実績、勝つ可能性はどのくらいで、どういう条件が揃えば勝機があるのか、そんな解説抜きに「勝つでしょう、がんばれ」と応援団になるだけの解説者が多すぎる。だから敗因の冷静な分析もできないのではないか。
そんなわけで、ぼくはオリンピック観戦は好きでない。
だいたいメダル獲得競争と、日本選手の応援ばかりでうんざりなのだ。
思い起こせば、中学生だったぼくの記憶に残っている東京オリンピックは、
マラソンのアベベ、体操のチャスラフスカ、十種競技の楊伝広、柔道のヘーシンク、棒高跳びのハンセン、そして女子バレーボール(たしか、全日本チームではなくニチボー貝塚だった)。
要するに、「すごい!」とうならせる選手が印象に残っているのだ。
ネットで検索すると日本の応援ばかりなのだが、書籍を検索してみると2020年の東京オリンピックに異議を唱えている本がけっこうある。そのうちの一冊を買って読んでみた。
小川勝『東京オリンピック 「問題」の核心は何か』 (集英社新書、2016.08.17)
まずオリンピック憲章の詳しい説明があり、それに対して日本政府が2015年11月に閣議決定した「基本方針」がいかにオリンピック憲章に反しているかが順々に説明されている。
「憲章1-6、オリンピック競技大会は…国家間の競争ではない」
そう、だいたい分かってます。オリンピックの主催は国ではなく都市であり、ブラジルは大統領不在でも開催できたし、オリンピックの旗は小池百合子さんが引き継ぎました。でも入場は国別だし、表彰式では国旗が掲揚され国歌が流れる。それに閉会式の主役は総理大臣の安倍さんだった。どうして?
「憲章5-57、IOCとOCOG(組織委員会)は国ごとの世界ランキングを作成してはならない」
国家間の競争じゃないのだから当然だと思うが、でもここまではっきり明文化されているとは思わなかった。じゃあ国ごとのメダル競争はマスコミがあおっているだけか?いやいや日本政府も組織委員会もメダルの目標を具体的に数として公表しているぞ。じゃあ憲章違反じゃないか。
著者は単純なメダル獲得競争は無意味だという。たしかにちょっと考えてみても、水泳や陸上は個人で複数個のメダルを取るのが可能だし、柔道やレスリングは特定の国が多くのメダルを取るのが可能だ。しかしサッカーやバレーボールはそうはいかない。
その他、オリンピックを政治的、商業的に利用してはならないとも述べられているのだが、東京オリンピックは経済効果ばかりを謳っているではないか。しかも、過去のオリンピックを振り返ってみると、開催国民は利益を得てないという。
記憶をたどれば、大昔はオリンピックにプロ選手は出られなかったし、国歌演奏がなかった時もあったような…。
では、どうして憲章に違反するようなことが何年も堂々と続いているのか、オリンピックはこれからどうあるべきか、そのような分析や提言については、この本はちょっと物足りない。
2016年9月21日 記
ルソーの新訳
ルソーの新しい翻訳が出た。
先月講談社から 『人間不平等起源論』 の新訳がでたばかりだ。
増田真訳『言語起源論 -旋律と音楽的模倣について-』(岩波文庫、2016.08.17)
解説を入れても153ページの小著である。
言葉はもともと文字に書かれたものを読むのではなく、詠唱されて聴くものだった。古代ギリシャのホメロスしかり、コーランしかり。それがどういう具合に堕落し退廃していったのか、それがルソーのモチーフだ。
それにしてもどこで学んだのか、ルソーの博学には驚く。
たしかに日本でも『平家物語』は歌によって伝承されていくものだった。
齋藤孝『声に出して読みたい日本語』(草思社、2001)の指摘を待つまでもなく、名作といわれる文章は読んで聴いて心地よい。「学問の自由はこれを保障する(憲法23条)」はとってもリズミカルだ。「これを」は何を指しているんだ、意味不明だなんて言わないことだ。
ルソーの翻訳あれこれ
ところで、
ぼくは昔この本を日本語で読んだ。
小林善彦訳『言語起源論』(現代思潮社1976.03.30) である。
訳者の小林先生は、中央公論社の『世界の名著』シリーズのルソーの巻で『人間不平等起源論』を翻訳された当時若手のルソー研究者であり、ぼくは大学でルソーの『告白』を習った。だからこの小林訳には愛着がある。
小林訳はアマゾンで検索したら今も入手可能なようだ。
外国の名著と評価される作品には、たいてい複数の翻訳が出ている。
・訳が間違っているのを憤慨して別な人が新訳を出すという場合が当然ある。
・原著は何も変わっていないのに、翻訳の日本語が古くなって読みにくいので新訳が出るということもあるだろう。
・すでに出版された翻訳が素晴らしいのにまた新訳が出るということもある。訳者の解釈が違っているからだ。前回紹介したアリストテレスの『ニコマコス倫理学』もそのような例か。
そもそも外国語をそのまま日本語に移すのは不可能だ。
I am a boy. これを日本語に翻訳して、
・俺は男だ。
・ぼくは男の子だよ。
・私は少年です。
・拙者は児童でござる。
どれも日本語としては不自然だよ。
だから既訳に不満な人はどうしたって新訳をだしたくなる。
ところでルソーの 『エミール』 を引き合いに出すと、ぼくは今五種類の翻訳を持っているのだが、おそらく一番普及しているのは岩波文庫版だろう。それは1962年が初版で、五種類の中では一番古いのだ。つまり、他の翻訳は岩波文庫版を当然参照し、それよりも正確で読みやすい翻訳を目指したと思われるのに、依然として岩波文庫版が普及し、学術論文で『エミール』を引用する人もほとんどが岩波文庫版に拠っているのだ。
本に限らず電化製品でも食料でも、一番良い物が一番普及するとは限らない。安いとか宣伝が巧みとか大会社だからとか、手近に手に入るとか…。
コメニウスの翻訳
話は変わるが、退職後は毎日コメニウスのあまり知られていない著作を読んでいる。昨年2015年2月に 『パンパイデイア』 を翻訳出版し、ようやく次の本の翻訳が近々出版されるはずだ。
その出だし Institutum nostrum est, ....
これを「私たちの意図は...」と訳したが、「わたしたちの」「我々の」「われわれの」あるいは「わが」とするか、あるいは思い切って単数と解して「私の」「わたしの」とするかで、すでに何種類もの訳が考えられる。次に Institutum の選択肢として「意図」「目的」「計画」「企て」などが想定されるが、どれがいいだろうと考えると本当に困ってしまう。この場合、ぼく自身の好きな語感はあるのだが、さてコメニウス先生はどの語感がお好きだろう、と考えると悩んでしまう。
ま、意味さえ通じれば、細かいことはどうだっていいじゃないか、と割り切ってしまえばいいのだが。
ついでにもう一つ。
1960年に翻訳されたコメニウスの 『大教授学』 。今では絶版で手に入らない。でも「主著」と見なされて、特に第6章の「人間には教育が必要だ」という箇所はしばしば引用される。
しかし日本語で「教育」と訳されている箇所の原文は、formare(形成する)、disciplina(訓練)、cultura(耕作)などであり、今日の education の元になっている educatio はいっさい使われていないのだ。
これはぼくには注目すべきことだと思われ、新訳を出したいという願望がいつもあるのだが、「そんな細かいことにはこだわるな」と笑い飛ばされそうな気もする。
2016年9月3日 記
夏はやっぱり暑い
このページの更新が、5月末以来2か月以上止まっていた。
忙しかったから、というのが直接の理由だが、何も書くことが無かったから、というのが本当の理由だ。
何も書くことが無かったというより、掲載するようなことがなかった、というのが正確か。この間、世界各地でのISのテロ事件、東京都知事の辞任と選挙、参議院選挙、そしてオリンピックと、日記に書いたことはたくさんある。 (しかしそれは公開を予定していない、ディスクの中だけの、死期が迫ったら数秒で消却するつもりのものだ。)
このページは読書感想文を中心にしよう(それ以外のことも書いてあるけれども)という心積もりだったものだから、あまり読書してないので書くことがなかったのだ。
いや読書をしてないわけじゃない。特に、ことしから非常勤講師を始めたものだから、授業の材料を新たに仕入れるための読書にはかなり時間をかけた。あ、でもそれは普通読書と言わないな。
それと、コメニウスの次の翻訳の出版が秒読みに入り、そのための復習も結構大変で、昔読んだいろんな本を再読した。
さらに付け加えると、4月から始めたギリシャ語の勉強が予想通り大変なのだ。
(この二つについては後日詳細に紹介するつもりです。)
そのため、退職後の希望であった、専門の研究書以外の本を楽しんで読むという時間がなかなかとれないのだ。
この間に読んだ本といえば、
『世界の名前』(岩波新書、2016.03)
くらいかな。
古代ギリシャではプラトン、ソクラテスと個人名だけなのに、ローマになるとマルクス・トゥッリウス・キケロとかガイウス・ユリウス・カエサルなどと長くなる。韓国の名はペとかイとかとても短い、などなど、国によって事情がとても違うことに前から興味があった。
そのようなぼくの興味に直接応える内容ではないけれど、世界各国の百以上の地域の名前にまつわる話が満載でおもしろい。「夫婦別姓が日本の伝統だ」などという主張が世界には通用しないことがよく分かる。
さてどうしても自分の研究分野に近い本の出版に目が向く。注目の新刊二冊。
ルソー著、坂倉裕治訳『人間不平等起源論』(講談社学術文庫、2016.06)
コンディヤック著、山口裕之訳『論理学』(講談社学術文庫、2016.07)
ルソーの不平等起源論はこれまでに何種類も翻訳が出ており、これは新訳だ。格差社会の今日、不平等を改めて考えようということなのだろうか。なお、「戦争法原理」というあまり知られていないルソーの論考の翻訳が付録についている。これも現代の読者に響くという趣旨なのだろうか。
コンディヤックの翻訳としては『人間認識起源論』が岩波文庫に収録されているが、この『論理学』は初訳だそうだ。こういう古典が翻訳されるのはうれしい。
枝葉末節かもしれないが、この二冊の講談社学術文庫のカバーが気になった。
『人間不平等起源論』のカバーは当時の原典に付けられていたいわゆる未開人の絵だ。だからコンディヤックの『論理学』のカバーの絵も当時の原典に使われていた挿絵かと推測してしまう。キューピッドのような少年が ΕΙΣ ΦΑΟΣ と書かれたプレートを掲げているのだ。これは「光へ向かって」というギリシャ語であるくらいはぼくでも分かるのである。いかにも啓蒙思想家のスローガンだと感心。ところが、カバーの見返しには「ジョージ・バンクロフトの蔵書票」だとある。たしかに断ってあるからいいのだが、ちょっと誤解を与えそうだ。


2016年8月8日
『名作うしろ読み』
ある新聞に大きく紹介された。
読売新聞の夕刊に連載されていたらしいのだが、まったく知らなかった。
2013年1月に中央公論から単行本となって出版されたのだが、それも知らなかった。
「うしろ読み」などという言葉、聞いたこともなかった。
要するに、名作の最後の締めくくりの一文を集めたのだ。
そうか、出だしの一文はけっこう有名でも、最後は意外と知られていないな。でも著者は力を入れて書いたはずだ。
今回2冊目が新刊として出版され、前作は文庫になったので読んでみた。
斎藤美奈子著『名作うしろ読み』(中公文庫、2016.01)
斎藤美奈子著『名作うしろ読み プレミアム』(中央公論新社、2016.02)
ぼくはいま小説はほとんど読まないのだが、少年時代は名作と呼ばれるものはかなり読んだのである。
子供向けの世界文学全集を親が買ってくれたし、
漱石や鴎外はほとんど読破したはず。
松本清張と森村誠一も文庫になっているものはたぶん全部(かな?)、
カラマーゾフ、ジャン・クリストフ、戦争と平和、風と共になど、長編も受験勉強の合間に読んだ。うーん、最後の一文はどうだったかなあ。
斎藤美奈子がまず取り上げたのは、『坊ちゃん』の最後「だから清の墓は小日向の養源寺にある」。そうだったかもと記憶の片隅にあるようなないような。
ぼくは授業の時に、親でも教師でもないのにものすごく影響を与えた人の代表例として清を紹介してきたのだ。でもぼくが思っていた以上に清は坊ちゃんにとって大切な人だったのだ。なるほど、深い読みだと感心した。
そして最後は『共産党宣言』の末尾「万国のプロレタリア団結せよ!」だ。これはぼくも知っている。でも最近あまり聞かないかも…。グローバル経済の中で、今こそ万国の労働者は団結しないといけないんじゃないかな。
少し大きな書店には文庫本がたくさん積んである。だからこの本もすぐ見つかるだろうと思っていたら甘かった。1月発行なのでもうどこの本屋にも積んでないのだ。ようやく3軒目で1冊だけ棚に並んでいるのを見つけた次第。
神、天使、キリスト…
毎日とにかくコメニウスの「パンソフィア」を読んでいるのだが、5月に入ってから難行苦行である。
そもそもコメニウスはいつも聖書からたくさん引用しているのだが、今読んでいる章は聖書や宗教を直接論じているところなので、何を言わんとしているかチンプンカンプンなのだ。若い頃に読んだ時は章題と目次を見ただけでスルーしたのだが、今はとにかく読破しようと決めている。それにしても分からん…。
そこで今月の新刊の
山内志朗著『感じるスコラ哲学』(慶應義塾大学出版、2016.05)
を買ってみた。
もよりの三省堂にも有隣堂にも置いてないからアマゾンの「画期的な中世哲学入門書」という宣伝を信じて注文したら当日届いた。
まず出だしからして漱石の『門』の引用から始まる。通れないと分かっている門の前で、引き返す勇気もないままにたたずんでいる主人公宗助と著者は同じなんだそうな。キリスト教徒でも西洋人でもない現代日本人が、門の外に佇んで苦いスコラ哲学を毎日味わっている状況が縷々述べられている。
そんなの楽屋の内輪話としてやってほしいよ。こっちには山内さんの愚痴に共感する余裕はありません。最後は「話が屈折している」が「道草をご相伴してくれる人」がいることを期待しているらしいのだが、ぼくにお相伴するゆとりは今はない。
この山内志朗さん、中世についての本をたくさん書いているので、もう少しお相伴しようと思い、
山内志朗著『天使の記号学』(岩波、2001.02)を図書館で借りた。
コメニウスの本に神だけでなく天使の話もどっさり出てきて、これまたぼくにはつかみ所がないから、この本に何か参考になるようなことが書いてないかと思ったのだ。
でもこの本の出だしも変だ。「自分ということのリアリティを見失ったとき…たばこの火を体に押しつける行為は特異なことなのだろうか」で始まる。夢じゃないかとほっぺたをつねる事例はよくあるし、若者のリストカットも聞いたことがあるが、たばこの火を自分の体に押しつける人なんて、いるのか? どうもこの人は特異な人らしい。
あとがきも変だ。「私はもともと献呈の言葉というのが大嫌いである。…しかしながら」と亡き父にはじめての本を献呈した時の思い出がていねいに綴られている。このようなエピローグ、ぼくは大嫌いだ。
天使のことはちょっと出てきただけだったので、たまたま今月の中公新書の新刊の
岡田温司『天使とは何か』(中公新書、2016.03)を買ってみたのだが、これも期待外れだった。
ぼくの頭が、複雑な論理を受け付けないほどに老化してしまったのではないかと心配だ。
なお、ギリシャ語の勉強については、別ファイルに書きました。
2016年5月
最近読んで面白かったのは
若原正己著『ヒトはなぜ争うのか 進化と遺伝子から考える』(新日本出版社、2016.01)だ。
21世紀になって平和な時代がようやく訪れるかと思ったのに、冷戦時代よりもひどい戦争やテロによる殺戮が至る所で横行している。そして日本の指導者は憲法を無視して軍備を増強している。
ところでこの著者も述べているように、文明の発祥と言われる古代ギリシャやローマでも戦争の連続だった。
大河ドラマはだいたいが戦国時代の戦いか幕末の動乱が舞台だ。
おそらく、アニメやゲームでも戦いの場面が主流なのではないか。
そうなると、争いは人間からなくならないと悲観的にならざるをえない。
殺戮の戦争とまでいかなくても、他人を上回ろうという競争心・闘争心は人間からなくならないのではないか、そんな思いで題名に引かれてこの本を買った。
人間には「争う遺伝子」が組み込まれているが、それを抑制するのか発現させるのかは人間次第だということになる。人間にはその遺伝子をコントロールする力(ふつうは理性と呼ばれている)があり、それは他の動物には見られない。だから人間が好戦的になるか反戦になるかは、教育と宣伝の力が大きい。それが著者の結論だ。
さて、現状の教育と宣伝(主にマスコミの)を見るにつけ、どうしても好戦的な遺伝子を刺激しているとしか思えない。何とかせねば。
2016年4月30日 記
オール沖縄の闘い
昨年の5月に、沖縄選出の参議院議員糸数慶子さんの講演会があったのででかけたことはこの日記に書いた。
今度は沖縄選出の衆議院議員の仲里利信さんの講演会があったのでやはりでかけた。
糸数さんは沖縄社会大衆党だが、仲里さんは元自民党員で県会議長まで務めた重鎮である。
もう高齢なので引退するつもりだったが自民党を離党し(除名されたと言う)革新統一(いや、今はこういう表現は使わないか、野党共闘、オール沖縄というんだろうか)で立候補して当選した人である。話にはでなかったが、離党や除名などの苦労はぼくらの推測できる範囲をこえているのだろう。
直接のきっかけは、沖縄戦での住民の集団自決の表現が教科書から削除されてしまったことに憤慨したということらしい。防空壕に潜んでいた仲里少年は、幼い妹が泣きやまない時に兵士が毒入りの饅頭を持ってきて食べさせようとしたことを鮮明に覚えているという。その他のエピソードは書ききれない。とにかくどこにもすごい人がいるものだ。
2016年4月23日 記
アリストテレスのニコマコス倫理学
新聞の下欄に載っている本の宣伝を見ていたら
菅豊彦著『アリストテレス「ニコマコス倫理学」を読む』(勁草書房、2016.02)
が目にとまった。
『ニコマコス倫理学』はもちろん所有しているし、不遜ながら授業でも扱ったことがある。どんな読み方をするのか、書店で立ち読みしてからと思ったのだが陳列してなかったのでアマゾンで注文して読んでみたのだが…
率直に言っておもしろくなかった。就寝前の明晰でない姿勢で読んだからかもしれない。
注目したのは、前書きで「翻訳が五種類ある」と記してあったことだ。
ぼくが所有しているのは岩波文庫版だ。その他に、新旧の全集に収録されているのは想像がつく。さらにその他に京都大学学術出版会の西洋古典叢書シリーズ、さらに光文社古典新訳シリーズに収録されている翻訳があるのだった。
光文社の古典新訳シリーズは駅前の書店に置いてあったので早速購入した。その他は高価なのでちょっと…。
光文社版のあとがきで渡辺邦夫は、
岩波文庫の高田訳は、正確で水準が高く、
旧全集の加藤訳には、常識を覆す訳語に衝撃を受け、
京大の朴訳は、完成度が高く正確で、
新全集の神崎訳には、新アイデアがこめられているという。
ところでぼくは学生時代に『ニコマコス倫理学』を読んだ時に、幸福とは何かをさんざん論じながら、結論は「中庸」だというその平凡さに多少失望したものである。
しかし今あらためて読んでみると、勇気の過剰は無鉄砲であり勇気の過小は臆病ということになり、ほら、中庸が大事でしょう、という結論には異論の出しようがない。そしてアリストテレスをよく読んでみると、過剰の程度と過小の程度によって中庸の位置は移動する、それをよくよく考えるのが大事だということになる。
これはどの「徳 アレテー」にも当てはまるから、現実を念頭において読んでいくとけっこう楽しい。
ささいなことかもしれないが、菅豊彦の著書でも光文社版でも、ギリシャ文字がいっさい使われていないのに気づいた。本文はもちろん注にも出てこない。
「幸福 エウダイモニア」とカタカナか eudaimonia とローマ字で表記されているのだ。
たしかに、いちいちギリシャ文字で εὐδαιμονίᾱ と書かれたのではふつうの読者は読みにくいし、おそらく印刷上も不便なのだろう。それにギリシャ文字とローマ文字は一対一に対応しているから、ギリシャ文字を使う必要はないのだ。
でも「アレテー」と書かれたら αρετη なのか αλεθη なのか分からないじゃないか、と文句を言いたい所だが、ギリシャ文字を読める人ならその位はすぐ判断できるということなのだろう。最近ギリシャ語の勉強を始めたばかりの個人的なつぶやきでした。
先月ホッブズのあまり有名ではなかった諸著作のことに触れたが、新たに
ホッブズ『法の原理―人間の本性と政治体』(岩波文庫、2016.04)
が出版された。
すでに伊藤訳『哲学原論 自然法および国家法の原理』に収録されているのだが、文庫の方が何かと便利なので購入した。きちんと読むのはこれから。
トマス・ホッブズ
先月も書いたように、これまで読んだことのないような分野の本を読みたいなといつも思っている。とはいえ、これまで親しんだ分野の新刊書にももちろん興味はある。
駅の書店で
田中浩著『ホッブズ』(岩波新書、2016.02)
を見つけてさっそく購入して読んだ。
大学に入学してすぐ、「社会思想史」の授業でホッブズ、ロック、ルソーをまとめて習った。水田洋訳の『リヴァイアサン』も買った。英語版も買った。ちゃんと読んだわけではないが。
ホッブズは90歳過ぎまで生きたが、著者の田中浩もことし90歳だ。すごい。
ホッブズの政治的立場は当時から微妙だったようだ。ピューリタン革命期はパリに亡命し、クロムウェル体制が確立してから帰国、しかし亡命時代はやはり亡命中のチャールズ皇太子の家庭教師も勤めていたという。
田中によれば、人間にとっての最高価値は「生命の安全」(自己保存)であり、平和が最優先だという。平和を維持するにはどのような政治体制(社会契約)が必要かというのがホッブズの課題であり、極端なことを言えば、平和であれば王党派だろうが革命派だろうがどちらでもよい、ということになる。ホッブズの言う「自然権の放棄」とは田中の解釈では「自分の武器を捨てる」ことなのだ。なるほど、そうか。
たしかに「命よりも大事なものがある」「命をかけて大義を守る」「◦◦のためなら命を捨ててもよい」という主張は昔からあふれているが、ホッブズはそのような考えを明確に否定したということだ。
ホッブズは主著の『リヴァイアサン』以外にもたくさん本を書いており、「すべての学問を研究したマルチ人間」だったという。晩年に『市民論』『物体論』『人間論』三部作を完成させた。つまり今で言う政治学だけではなく、数学も自然科学も哲学も研究していたのだ。もっとも彼の数学研究には当時から批判があって、ボイルの反対で「王立協会」へは入会できなかったらしい。
最後の章の「ホッブズの意義」はなかなか読みごたえがあった。
ホッブズを引き継いでロックやルソーの革命思想を学んだイギリスやフランスと比べて、ドイツでは、カントもヘーゲルもホッブズを理解できなかったという。そしてヴァイマール体制はヒットラーによって圧殺されてしまった。
ドイツに学んだ日本でも、大正デモクラシーが根付かずにファシズム体制になってしまった。ホッブズを学ばなかったのがその原因かどうかはおそらく議論になるところだと思うが、なるほどと思わせる。
田中の本書の結論は圧巻だ。昨年の安全保障関連法に反対し、「軍拡によっては戦争を抑止できない」「ホッブズが述べているように、各国が全力をあげて平和を守るために武器を放棄する以外にない」と。
田中の『ホッブズ』を読んで、ぼくが普段から抱いているのだが怖くて外に出せない考えがますます強まってきた。一言でいえば「正義のための戦争」「自由のための戦い」そして他国への軍事介入はいけないということ。
日本の明治維新、戊辰戦争や西南戦争など、内乱状態の兆しはあったが何とか自力で落ちついた。チトー亡き後、ユーゴは数年間内乱状態だった。世界各国が善意で介入した。アメリカがフセインを殺した後、イラクは今も混乱が続いている。そしてシリアのアサド政権。アメリカとロシアが綱引きしている。
人類の歴史をみれば、各地域の文明の進行状態には時間差がある。中国で孔子、ギリシャでソクラテスが活躍していた頃、日本にはまだ文字も存在していなかった。民主主義も人類共通の普遍的価値かどうかあやしい。北朝鮮の現在の政治状況は、100年前の日本と同じ、300年前のフランスと同じなのだ。
具体的に言うと、アサドを排除しても、アサド独裁時代よりも多くの人命が失われるのではないか。北朝鮮でも…(だから、この先は怖くて言えないんだよ…)
数日後、同じ書店に寄ったら、何とホッブズの『物体論』の翻訳が陳列されていた。750頁もの大著だ。すぐ検索してみたら、三部作とも横浜市立図書館に所蔵されている。
ホッブズ著、本田裕志訳『市民論』(京都大学学術出版会、2008.10)
ホッブズ著、本田裕志訳『人間論』(京都大学学術出版会、2012.07)
ホッブズ著、本田裕志訳『物体論』(京都大学学術出版会、2015.07)
さらに驚いたことに、『リヴァイアサン』の新訳が光文社から刊行中(全2冊のうちまだ1冊のみ)なのだ。
『市民論』『人間論』『物体論』の三部作を単独で翻訳した本田裕志は、『リヴァイアサン』のみでホッブズを評価する内外の状況を批判し、ホッブズの全体像を明らかにするためには三部作を視野にいれないと「本物とは言えない」と強調している。
その後に、実は上記の三部作がすでに翻訳出版されていることを知った。
伊藤宏之・渡部秀和訳『哲学原論 自然法および国家法の原理』(柏書房、2012.05)
横浜市立図書館に収蔵されていたので借り出してみると、上記三部作の他にホッブズの最も初期の作品『自然法および国家の原理』も収録されており、何と1700頁もある。重い。
実は田中の岩波新書の参考文献欄には本田訳も伊藤訳も載っているのだが、うかつにも気づかなかった。
本田訳では、翻訳にいかに苦労したか、そしてこの翻訳にどれだけの意義があるかが縷々述べられているのに対して、伊藤訳の序文は「本書の出版目的は、ホッブズ理解を進化することである」ときわめて短い。もちろんぼくの好みは後者だ。
さて、ざっと目を通した印象では、伊藤訳の方が断然読みやすい。
注や解説を見た限りでは、本田訳はラテン語原典に固執しているのに対し、伊藤訳は当時の英訳版を頼りにしているようだ。
全部を読んでないので(たぶん読み終えないだろう)軽率なことはいえないが、触発されたことは多い。
ホッブズはぼくが研究しているコメニウスと完全な同時代人である。ただし、コメニウスがイギリスを訪問した時にはホッブズはすでにフランスにいた。
ホッブズが『リヴァイアサン』の他に膨大な著作を書いていたように、コメニウスも教育の本以外にあらゆる学問分野に手を出している。そして両人とも哲学については、アリストテレスの古い枠組みに沿っている。
ホッブズの本にも宗教の問題、特に聖書からの引用が満ちあふれている。そもそも「リヴァイアサン」という題名が聖書の一節から採られたものだ。コメニウスの本にも聖書からの引用があふれていて、ぼくなど食傷気味なのだが、本田解説によればホッブズの宗教論を軽視するのは誤りだという。
ホッブズの人間論はまず光学の成果の復習から始まり、人間の視線の研究、そしてそれが人間の認識論へと発展する。この進行はコメニウスとほとんど同じだ。伊藤の解説によれば、17世紀の感覚論はまず「光学」を論じるのが共通だったという。
なるほど。コメニウスの『パンソフィア』をホッブズと比較しつつ読む必要があるかもしれない。
2016年3月31日 記
一年経ちました
昨年の3月に卒業式に臨席し、墓参りを済ませてから、横浜に移り住んで丸一年が経過した。もうずいぶん以前からこの生活が続いていたかのような気になる。
基本的な生活は、10月に書いたこととほとんど変わっていない。
朝起きて、朝ご飯を作って、洗濯して、時々掃除して、昼食を作って食べて、夕食の支度をし、夕食を食べて、ゴミをまとめ、風呂に入って寝る。要するに、家事の繰り返しだ。ちなみに、家事は嫌いではない。そして時々妻の送迎。
その他に、図書館にでかけたり、会合にでかけたりする。その会合は、付き合いが増えるにつれてだんだん増えつつある。ちょっと困っている。医者通いもしなければならない。
10月からは毎週1回ラテン語講座に通っているので、その日は帰りが遅くなる。
退職したら、ずっとほったらかしにしてあったコメニウスの文献を読もうと決めた。
4月は引越のゴタゴタ、5月は学会の原稿の校正、そして6月から7月にかけては再度の引越で、8月に入ってから Pansophia に本格的に取り組み始めた。1ページが2段組になっているのでそれを2頁と数えると、約1100ページある。
自分でも感心しているのだが、年末年始の3日間を除いて毎日読み進めている(それも、忙しいから休んだのではなく、体調が悪かったから机に向かわなかったのだ)。現役時代は、勉強時間がゼロだった日がけっこうあったと記憶しているから、すごいことだ。
それでもまだ500ページほど残っている。半分以上は読んだ、と前向きに考えるべきか。
内容はというと、正直いってあまり面白くはない。よく分からないのだ。
ぼくの手持ちの辞書に載っていない単語がある。
辞書に載っているのかもしれないが、原型が何なのか推測がつかない単語がある。
もしかしたらミスタイプなのかもしれない。
時々でてくるギリシャ語やヘブライ語が分からない。
一応訳せても何を言いたいのか意味不明なところが多い。
意味は分かったような気になるが、コメニウス本人がどういう意図でそう書いたのか分からない。
意味は通じたが、現代に活かせることなのかどうか、自信がない。
などなど。
それでも、もう少し続けてみようと思う。そのうち、急に目の前が開けてくるかもしれないから。
その他に、専門の勉強とは違う、娯楽としての読書をしたいと希望しているのだが、これは今のところなかなか難しい。
先に述べたように、10月からラテン語講座に通っている。4月からは新たにギリシャ語講座が始まるので、それに参加しようと思っている。実はギリシャ語はこれまで何度も挑戦しているのだが、ほんの入口で(ξ クシーがうまく書けないあたりで)挫折していた。さて、どうなるやら。
もう一つ大きな変化がある。
会津短大がこの4月から新しい学科、幼児教育学科を新設するのである。その非常勤講師になるのだ。
学科新設を文部科学省に申請するので協力してくれと懇願され、他に適任者がいるだろうにと断ったのだが、とりあえず業績書を送っておいた。幸か不幸か申請が認められたのだ。
そこで、会津まで通うことになったのだが、毎週通うのは大変だから一度に2コマこなして隔週授業することになっている。こちらは楽しみというより、心配だ。
実をいうと、もう一つ別の大学から講義を頼まれているのだ。こちらは来年の4月から新設予定の大学院である。
その予定科目はぼくの得意分野とずいぶんかけ離れているので、文部科学省の審査に通るかどうか、ぼくは案じている。審査に落ちたら、それはぼくの責任じゃないから、残念でしたと言うしかないのだが、もし申請が認可されたら、来年の春からは毎週通わないといけなくなり、しかも複数科目を担当するらしく、ほんとに心配している。微々たる報酬をもらって働きたくないのが本音なのだ。
それよりもやりたいのはジョギングだ。昨年秋からほとんど走れない状態が続いていたが、少しずつ走れるようになってきた。
当然のことながら、一回ジョギングすると事前事後も含めてどうしても1、2時間はかかる。外出する日はできないし、机に向かっているといつのまにか夕方になってしまい、走る時間が惜しくなる。雨や風をいとわずに走るほどの根性はないから、週に2回走ればいいほうだ。
そこで、これまでの「よこはま月例マラソン」の他にもう一つの月例会に参加することにした。こうして自分を強制すれば、少しは普段の練習にも励みになるかもしれない。
考えようによっては、いつ終わるか見当もつかないような研究の時間を削って健康作りの時間を増やす方が、自分には良いかもしれないのだ。
もう少し練習量を増やし、そのうち東京マラソンか横浜マラソンに出てみたいのだが。
2016年2月の読書
せっかく退職したのだから、これまで読んだことのないような分野の本を読みたいなといつも思っている。
そこで今月読んだのが、
小畑弘己著『タネをまく縄文人 最新科学が覆す農耕の起源』(吉川弘文館、2016.1)。
あとがきには「学術書ではなく、広く歴史好きな一般の方」向けの書物だとあるが、専門用語の難しい漢字もたくさん使われていて、なかなか読みごたえのある本だ。
縄文時代は狩猟採集社会と思われているが、農耕も存在していたのだ。ただしその場合の「農耕」の中身が問題になる。ついぼくらは農耕というと水稲栽培を念頭に置いてしまうが、日本人はコメ以外を長い期間食べていたのだ。
縄文土器の中に入っていたタネやムシが主人公である。
これまで土器の傷くらいにしか考えられていなかったものが、どうやらタネやムシの跡らしいと調べてみるとどんどん出てきたんだそうな。そしてエックス線で調べてみるとさらにゾロゾロ…、これを「潜在圧痕」というらしい。
ゾロゾロといっても、何万点もの土器からやっと数点発見されるという具合だから、大変な作業だと推測できる。
とにかく何千年も昔の話だからどうしても推測の域を出ない話ばかりで、ミステリー小説だと思って読むとおもしろい。
まず、著者たちがダイズの圧痕を発見したのが2007年。それがそもそもダイズなのかどうか、そしてそれが野生のものなのか栽培されたものなのか、という推理が続く。
たしかにぼくの個人的な経験からも、雑木林を歩いていて見つけた栗を持ちかえって食べようと思っても、とても小さくて食べようがないし、野イチゴも小さくて酸っぱくて食べられたものじゃない。
それでどうするかというと、一番大きな種実をまく、という作業を千年くらい繰り返すんだそうだ。著者はさらりと書いているだけだが、一番大きな食べごたえのあるものを食べずにまくなんて、なんて賢いんだろうと感心した。
縄文土器の中からコクゾウムシが発見されたのが2005年だそうだ。コクゾウムシは米に寄生する害虫だから、縄文土器の時代にすでにコメがあったと喜ぶのはまだ早い。コクゾウムシはダイズにも寄生する。そしてダイズに寄生するコクゾウムシと現在コメに寄生するコクゾウムシは大きさが違うんだそうな。寄生先のタネの大きさに合わせるのだ。そうするとやはり縄文時代にコメはなかったということになるらしい。
土器の表面にムシがいつくっついたのか、そして内部になぜムシが入り込んでしまったのか、結論は出ないのだが、様々な推理が展開されていてそこも興味深い。もしかしたら人間が土を練る時にわざと入れたという可能性すらあるのだ。
ところで、アマゾンで検索してみたら、縄文時代を扱った本はたくさんある。
山田康弘著『つくられた縄文時代』(新潮、2015.11)
篠田謙一著『DNAで語る 日本人起源論』 (岩波、2015.9)
などはそのうち読んでみたい。
駅前に大きな書店が二軒ある。
最近の出版界も格差社会というか、売れる本(あるいは売りたい本)は入口に積み上げられているが、売れない本は棚からすぐ消えてしまう。
新書のコーナーに行ってみると実にたくさんの種類の新書! 同じ著者の同じような内容の本が複数の出版社から出ている。人気タレントがたくさんのテレビ CM に出ているのと同じような現象といったら失礼か。
新書類は数か月経つと半値、さらに数か月待つと百円で古書店に並ぶのですぐには買わないようにしているのだが、今月はこれを買った。
草野隆著『百人一首の謎を解く』(新潮文庫、2016.1)
帯に「長年未解決だった謎に明快な解答を示す、百人一首の見方が変わる快作」と書いてある。
百人一首はとても有名なはずだから、謎なんて何も無いのでは?
でも実はぼくは百人一首をまったく知らないのだ。だから何が「未解決の謎」なのかがそもそも分からない。まあ、少しは百人一首のことを知っておいてもいいかなと思って読んでみた。
最初に謎が12個列挙されている。
1 いつ出来たのか。
2 誰が作ったのか。
どこを探しても解答は見つからなかった。そもそも昔のことなのだから、いつ誰が書いたのか分からないものはたくさんある。著者が無名のゴーストライターを発見したのかと思ったらそうではなかった。
3 何のために作られたのか。
蓮生という人物の注文に応じて藤原定家が作ったというのは Wikipedia にも書いてある。蓮生という人がどういう人物だったのか、それはこの本に詳しく書かれている。そして、どの部屋に飾るつもりだったのかという推測がこの著者の一番の論点らしいのだが、読んで見ても著者の推測しか感じられなかった。
4から10では、百という少数の中になぜこの歌が選ばれなぜあの歌が選ばれなかったのか、という謎である。
著者は不幸な歌人の歌が多いのが謎だというのだが、古今東西、そもそも歌は悲恋や失恋、適わぬ恋がテーマ、完璧なハッピーエンドの方が少ないんじゃないか。シャンソンの「愛の賛歌」だって歌詞は不幸で恐ろしい内容だ。歌人の代表作が選ばれていない謎というのも、ぼくから見れば当然のような気がする。
むしろ、定家の死後190年経ってから現在に伝わる完成形ができて、それがどうして今日有名になったかという後日譚の方が知りたかったな。
最近、不祥事が多いのかな?
不祥事、醜聞、スキャンダル、ゴシップなどを目にすることが多い。
ことしに入ってからだけでも、SMAP の解散騒動、ベッキーの不倫疑惑、清原の覚醒剤使用、甘利大臣の口利き疑惑、宮崎議員の不倫辞任、などなど。
その他にも、中学生いじめ殺人、スキーバスの転落事故、介護施設での老人墜落殺人などの事故や事件も多数。
国会議員の失言・放言は数知れず。
ちょっと待てよ、ぼくはいつも学生に「凶悪事件の実数は増えてない、マスコミの報道で目立つだけだ」と言い続けてきたのだ。
ぼくの場合、まさに醜聞を「目にする」ことが、マスコミを通して多くなっただけではないのか。
いくつか原因がある。
まず第一に、テレビを見る機会が多くなった。
これまでは朝食後8時頃には出勤しており、職場ではテレビはいっさい見ずに、帰宅後もせいぜいニュースのみ、という生活だった。
ところが今は朝ドラを妻と眺めて(しっかり見ているわけではない)それから場合によっては朝のいわゆるニュースショーを見ることもしばしば。
それと、昼食はほとんど家で食べているので、その時もついテレビをつけて、いわゆるワイドショーみたいなものを見る。
ちなみにテレビはシャープの42インチだ。
第二に、週刊誌の見出し。
これまでは短い通勤時間にせいぜいラジオを聞くだけだった。
今はたまに外出する際に、駅の売店や車内で週刊誌の見出しが目に入る(買いはしないが)。
第三にインターネット。
職場にはもちろんインターネットは完備されていたが、職場でネットのニュースなど見る暇はなかった。しょっちゅう来客があるのでネットサーフィンをしている余裕もなかった。それに自宅にはそもそもネット環境がなかった。
ところが今は室内にWi-Fi が完備されていて、居間にも寝室にもiPad が置いてあるから、ついついネットでニュースを見てしまう。
実に驚いたことに、ネットの主要なポータルサイトでまず出てくるのは耳目を驚かすような醜聞が中心で、それに評論家や素人のコメントが無数についているから、一度入り込むとどんどん時間を浪費してしまう仕組みになっている。
要するに、ぼくは今までよりも醜聞を目にする機会が多くなってしまったのだ。
でももしかしたらこれが標準で、今までのぼくの生活の方が仙人みたいだったのかも知れない。
とすると、普通の大多数の人はいつも醜聞に囲まれているということになる。大事な問題がたくさんあるだろうになあ。
2016年2月20日、記
2016年1月の読書
何か気軽に読めて、しかもためになる新刊本がないかと考えていて、新聞広告に出ていたこの本を購入した。
仲谷正史、筧康明、三原聡一郎、南澤孝太著『触楽入門』(朝日出版、2016年1月20日)だ。
帯に付いている台詞「つねにネットに接続し、皮膚感覚を失っていく私たち。
さわってないのに、わかったつもり?」に興味を引かれた。
そう、アリストテレスが「感覚のうちで最も愛好されるのは眼による視覚である」と述べて以来、洋の東西を問わず(Seeing is believing、百聞は一見にしかず)、視覚が最も重視されてきた。
「見てもよく分からないものは触ってみればよい」と確かベーコンが述べていたような気がする(どこで述べていたか今は正確には思い出せない)。でも結局、触覚は他の感覚(視覚、聴覚、味覚、臭覚)より重視されてこなかったことは事実だ。
しかし、見るだけ、聞くだけではなく、実体験、それも体全体で感じ取ることはとても大事だし、そもそも人間は新生児から幼児にかけては触覚の世界で生きているのはフロイトの口唇期、肛門期の指摘を待つまでもない。
それに頭で考える時にだって、「本質を捉える」「状況を把握する」のように「手」で掴むことが必要なのだ。
そんなことを考えて読んでみたらけっこう面白かった。
さっそく図書館(横浜市立)に行って調べてみた。
何と、予想以上に、触覚に関する本がたくさん並んでいる。それも、人文科学と社会科学の両方のコーナーに。
『触楽入門』の著者たちはすでに『触覚をつくる』(岩波科学ライブラリー、2011)という本を公刊していた。
何冊か借りて読んで、特に興味深かったのは、以下の2冊。
・渡邊淳司『情報を生み出す触覚の知性』(化学同人、2014)
・傳田光洋『皮膚感覚と人間のこころ』(新潮選書、2013)
渡邊は NTT コミュニケーションの、 傳田は資生堂の研究員だ。
触覚があまり重視されてこなかったのは、どうやらいろいろ理由があるらしい。
視覚は眼に、聴覚は耳に集中しているのに対して、体中に触覚の神経が張り巡らされていてとりとめがない。
また、見た結果は写真や映画などで再現でき、聞いたこともレコード、CD などで再現できる、匂いや味覚も人工的に再現できるのに、触覚はどうも再現しにくい、なにしろ数値化できない。
さらに、たしかに眼にも耳にも錯覚や幻覚があるにはあるけれども、触覚の場合はどうしようもないくらい実に主観的で人様々だ、等々。
それでも最近は指や全身に張り巡らされた触覚のセンサーの研究が進み、脳との関係も明らかになってきたらしい。触覚を人工的に作り出す装置も開発されているとか。
ところで人間は自然界の一定範囲の光しか感じない(紫外線と赤外線の間)。また一定範囲の音しか聞き取れない。それに対し、人間以外の動物の中には人間が見えない、聞こえないことを感じ取る力があることが知られている。
そして注目すべきことに、人間の皮膚には、眼で見えない、耳で聞こえない刺激を感じ取る機能があるらしいのだ。そうなると、これまで単に「気のせい」で済ませてきたことも、実は肉体的な根拠があることになる。これはすごい。
上記の著者たちが述べていることではないのだが、触覚の仕組みが明らかになってくると、新しいデジタル機器が発達して、ますます人間がコントロールされることにもなりかねない。そういうことにならないよう、人間にとって最も原始的な触覚の本来の力を何とか生かして、情報化社会を生きて行くにはどうしたらよいか、考えさせられた。
このページの作成者・問い合わせ先:o-ta-ko-ich-de-su-yoあっとまーくnifty.com
last up date December 30, 2016
 コメニウス著、太田光一訳『覚醒から光へ:学問、宗教、政治の改善』(東信堂、2016.10.15)
コメニウス著、太田光一訳『覚醒から光へ:学問、宗教、政治の改善』(東信堂、2016.10.15)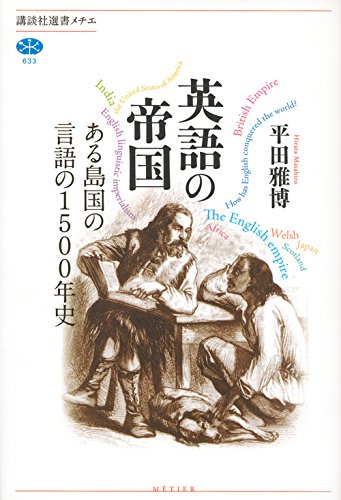 ロビンソンには彼の母語を学んで友だちになろうという気は最初からない。まず自分を「マスター」と呼ばせ、英語を教えて忠実な召使いとして仕えさせようとしたのだ。そうか、言われてみればそういう話だった。
ロビンソンには彼の母語を学んで友だちになろうという気は最初からない。まず自分を「マスター」と呼ばせ、英語を教えて忠実な召使いとして仕えさせようとしたのだ。そうか、言われてみればそういう話だった。
 表紙の女の子が枕にしているのは、ぼくが学生時代に出版された中央公論社の世界の名著シリーズの一冊。どの巻かまでは見えない。それと岩波のプラトン全集の第9巻ゴルギアス。「現代フランス哲学」という背が見えるがそれ以上は不明。それにヴィトゲンシュタイン全集第1巻。
表紙の女の子が枕にしているのは、ぼくが学生時代に出版された中央公論社の世界の名著シリーズの一冊。どの巻かまでは見えない。それと岩波のプラトン全集の第9巻ゴルギアス。「現代フランス哲学」という背が見えるがそれ以上は不明。それにヴィトゲンシュタイン全集第1巻。
